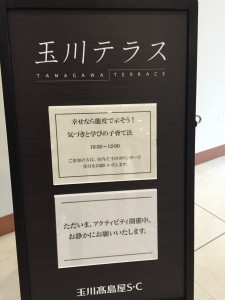<こひつじかい> 春のスキーキャンプ 1日目
2016年3月29日 / 未分類
3月25日朝6時半、朝日とともに子ども達が集まってきました。朝早くから元気いっぱいです。うれしそうな笑顔で新幹線記念撮影をして、お母様方に恒例のいってきますのハグをしたらさあ出発です。北陸新幹線「あさま」の中では、折り紙を折ったり荷物台にのぼって遊ぶなど、思い思いに元気よく遊びました。あっという間に長野に着き、無事にしなの鉄道に乗り換え、妙高高原へ向かいます。長野の駅からはもう雪が降っていて、銀世界の車窓にくぎ付けになり、子ども達はスキーをしたいと興奮していました。妙高高原駅では、ロッジ・ラーの方やコーチ達が迎えに来てくれていました。
![20160325_3113[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/20160325_31131-300x225.jpg)
![20160325_5875[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/20160325_58751-300x225.jpg)
![20160325_7308[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/20160325_73081-300x225.jpg)
![20160325_6863[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/20160325_68631-300x225.jpg)
朝早い出発で、ロッジ・ラー到着も予定より早く、11時にはお昼ごはんを食べました。行列のできるカレー屋さんに、みんな沢山お代わりをしていました。12時からは早速スキーです。グループに分かれ、それぞれのコーチとスキーレッスンをします。さっそくゲレンデに行きお約束をうかがった後、みんなたくさん練習をしました。なんと、泣く子はいません。それよりも、転んでも怖くても、スキーを滑ることがおもしろく、滑り終わった後はいつもいつも笑顔、みんなが楽しんでスキーをしていました。前日はあまり雪がなかったのに、今日までに50cmも積もっていました。ふわふわの雪で滑るスキーは最高です。初めてスキーをする子たちも、みんな滑れるようになりました。合計二時間半休憩もせずにスキーをしていました。上級班は、何回もカプセルに乗って新雪に挑んでいます。もっともっと上手になりたい気持ちで、コーチにたくさん質問しています。そんなふうにスキーに取り組む姿を見るのは、本当にうれしいです。
![20160325_3135[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/20160325_31351-300x225.jpg)
![20160325_1514[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/20160325_15141-300x225.jpg)
![20160325_2709[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/20160325_27091-225x300.jpg)
ロッジに帰ってきてみんなでお風呂に入り、美味しい夕飯を食べました。夕食後はみんなでお勉強です。美味しいご飯を食べて元気になった子ども達は、黙々と勉強をしていました。けんとくんは線をなぞるのがとっても上手でした。
就寝時間になると、たくさん遊んでたくさん食べた子ども達は、あっという間にみんなぐっすりと夢の世界で、気持ちよさそうです。一年ぶりに会うコーチからは、子ども達それぞれがお兄様やお姉さまに成長していて、またこのキャンプに一緒に参加できることがうれしいと言っていただきました。そして、最初はペンギンのようなよちよち歩きのスキーをしていたお友達が、小さい子ども達をサポートして、リフトに乗せるお手伝いをしている姿は凛々しく映りました。久しぶりに会うお友達もみんな仲良く、素敵なこひつじファミリーのキャンプ生活がスタートしました。明日も雪国の生活をたくさん楽しめる日になりそうです。
![20160325_2125[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/20160325_212511-300x225.jpg)
![20160325_3504[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/20160325_35041-225x300.jpg)
![20160325_223[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/20160325_2231-300x225.jpg)
![20160325_6676[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/20160325_66761-300x225.jpg)
![20160325_3247[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/20160325_32471-225x300.jpg)







![20160307_2671[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/20160307_26711-225x300.jpg)
![20160307_7383[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/20160307_73831-225x300.jpg)
![20160306 #1_4568[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/20160306-1_45681-225x300.jpg)
![20160306_683[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/20160306_6831-300x225.jpg)
![20160306 #1_8532[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/20160306-1_85321-225x300.jpg)
![20160306_4378[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/20160306_43781-300x225.jpg)
![20160306_3585[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/20160306_35851-225x300.jpg)
![20160306_8935[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/20160306_89351-225x300.jpg)
![20160306 #1_1973[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/20160306-1_19731-300x225.jpg)
![20160307_1405[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/20160307_14051-225x300.jpg)
![20160307_3883[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/20160307_38831-300x225.jpg)
![20160307_2300[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/20160307_23001-300x225.jpg)
![20160306_9537[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/20160306_95371-300x225.jpg)
![20160306 #1_1750[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/20160306-1_17501-225x300.jpg)
![20160307_3420[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/20160307_34201-300x225.jpg)
![20160307_9112[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/20160307_91121-300x225.jpg)
![20160307_8095[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/20160307_80951-300x225.jpg)